選考委員
第4回「近松賞」選評委員のコメント

第4回「近松賞」選評
選考委員 岩松 了氏
- 1952年生まれ
- 劇作家、演出家、俳優、映画監督

第4回「近松賞」選評
選考委員 栗山 民也氏
- 1953年生まれ
- 演出家
- 新国立劇場演劇研究所長
風景が見え、温度が伝わってきた
最終選考に残った十本の作品を読み終えて感じた、二つのことから書いてみようと思います。まず、近松賞という名称からでしょうか、また第二回目に『元禄光琳模様』が受賞作に選ばれたことも関係あるかもしれません、十本のうちのその半数が江戸期を題材にしたものでした。なにも歴史劇を問題にしているのではないのですが、その作品の多くが、史実と作者のフィクションがうまく綯い交ぜになってはいるものの、物語が横に並列的に、パノラマ風に動いていくのです。
たとえば、時代物でも作者のギリギリ絞り込んだ独自な視点と方法で、ある人物、ある場所、ある時といった作者の絶対的な作劇上の核を、思いっきりクローズアップした作品があってもよかったのではないか。
近松門左衛門の、あの革命的な現代劇の劇作家としての視点から描かれた、新しいカタチの現代演劇のための戯曲に出会いたかったのです。
二つ目は、僕が演出という仕事を中心にしているせいか、戯曲を読みながら戯曲の生命であるセリフを、いろいろな声に置き換えて聞こうとしているということがあります。もちろん、戯曲の言葉は役者の肉声によって再生されることを前提に書かれたものですから、声としてつまらない言葉でれば、すぐに劇の流れはその場で中断してしまいますが、そのときの感情や人物の動きをしっかりとスケッチした言葉であれば、生きた声として聞こえてきます。そして、その人間のスケッチを描くためには、そのまえに確かなデッサンによる無数の線の輪郭が必要となるでしょう。セリフが交わされるときに、果たして、活字である言葉が人間の声として立ち上がり、動き出していくのか。
そんなことを考えながら読み進め、二つの作品が残りました。
田辺剛氏『ある辺境にて』は、「知らない時代の、遠い世界のこと」という設定がありますが、一本の国境線がどんどんとずれて隣国の領域を侵犯していくといった、現代史を鏡に写し出されています。
ラストシーンに用意された、残された「土地」の妙に乾いた風景には忘れていた多くのものを思い起す力があって強く感動したのですが、四年前に上演したチリの作家アリエル・ドーフマンの『THE OTHER SIDE』との発想の類似点が、多少ちらつきました。しかしながら、国境を持たぬ日本人の意識から、ある距離感を持ってこのような主題が冷静なセリフで描かれたことに、強く興味を惹かれました。
『螢の光』は、とにかく、読み進めていくうちに人物から細部の小道具までが、可笑しな日常の風景としてぐんぐんと見えてきました。そして、初夏のむっと汗ばむ温度や湿度までが伝わってきました。
十作品のなかでは、ゾクゾクするほどに屈折を続ける感情の描写が、劇を前へ前へと動かしていくのです。その流れにまんまと乗せられてしまったのでしょうか、ちょっと固ゆでのソーメンを食べたときのような、妙にさわやかな読後感でした。
角ひろみさん、おめでとうございます。

第4回「近松賞」選評
選考委員 別役 実氏
- 1937年生まれ
- 劇作家
- 兵庫県立ピッコロ劇団代表
現代劇の現代性を推す
私は今回、最終的に『螢の光』を受賞作として推した。
この作品は、平凡な市井の人々の内にひそむ対人関係の不安を形にしたもので、舞台も「尼崎」という特定された地域に限定されているが、だからこそ逆に、現代人に普遍的な底深い崩壊感を写し出したものと言える。
手法は一見して平凡であり、平田オリザ風の「写実劇」の趣きを呈しているが、にもかかわらずその底に、奇妙な歪みのようなものを抱えこんでおり、トータルに読みこなすと、一種の不条理劇であることがよくわかる。
『蛍の光』というタイトルは、団地の窓と窓とで交される、光による合図に由来するのであるが、これも、現代人の錯綜した対人関係や、そこでのもどかしい、それだけに切迫した交流を物語るものとして、的確である。
ただし、技術的なことではあるものの、前半に一度これが使われただけで、後半にこれが出てこないのが、やや物足りない。形を変えてでも、もう一度これが虚しくまたたく、ということがあってもよさそうな気がするのである。
もうひとつ特筆すべきことを挙げれば、方言が上手く使われている、という点であろう。
現在、各地の演劇で多く方言が使われはじめたのは、少しばかり普遍性を欠くことになったとしても、特定地域の内密なコミュニケーションを重要視しはじめたからであり、肌から肌、伝達される言外のニュアンスを大切にしようという精神から出たものであるが、それがよく果されている。
「尼崎」という所は、方言的には混在地区であり、ピッコロ劇団の創始者である故・秋浜悟史氏は、これをこのまま「尼弁」として定着させようとしたが、この作品はまさしくその意を汲むものと言える。
その意味でもこの作品は、意義あるものなのである。
その他の作品では、今田三保子氏『睡蓮』と藤澤大介氏『我が名は』に注目した。
『睡蓮』は、演劇としては手法的にいくつか問題があるものの、詩的なイメージとしては独自のものを持っており、それをそのまま素直に表現しているという点で、好感を持った。
舞台の展開が、時間の経過に従って並べられており、フラッシュバックなど手のこんだことをやるより、それはそれで洒落ているのだが、イメージを積み重ねたり、構築するという作業は、やはり必要だったように思うのである。
そしてもうひとつ、この主人公の女性と若い青年のバックグラウンドとなるべき、子供を生む夫妻のドラマが、敢えて登場させない手法もないではないものの、もうひとつはっきりしない。
このドラマが、何らかの形で体感出来れば、主題も立体化されるのではないかと考えるのである。
『我が名は』は、『忠臣蔵』に現代的な解釈を加えたものであり、市井の「うわさ」の怖さというものを採り上げている、という点で面白かったのだが、不満なのは、実は大名がこれを流していたという点である。
大名の方もまた、「うわさ」の渦中にあったということになれば、まさしく現代的となったのではないだろうか。

第4回「近松賞」選評
選考委員 水落 潔氏
- 1936年生まれ
- 演劇評論家
- 毎日新聞客員編集委員、日本演劇協会常任理事
「近松賞」選評
最終選考に残った十作品は力作揃いで応募作の水準の高さを示していた。
受賞作の『螢の光』は市営団地に住む小企業の営業マン井上勉の妻晴子が「蛍を見に行く」と言って家を出たまま姿を消してしまったことから始まる。
二人は同じ団地で育った同級生だったが勉には思い当たるふしがない。しかしその後訪ねてきた中学生時代の鈴子、生協仲間の林の妻の話から、勉の知らなかった晴子の姿が見えてくる。どうやら晴子は向かいの棟に住んで居た林と共に消えたらしい。
勉はそれを知ってもとりたてて何か行動しようとはしない。平凡な家庭を覆う倦怠、夫婦とはいっても相手のことは何も知らない孤独、自分の殻にこもって生きている現代人の無気力が描かれている。私はムードに偏り過ぎて作者が何を言いたいのかが判然としない感を持ち、別の作品を推したが、現代人の心の闇の深さを描いた作品であるのは確かで受賞に異議はない。劇の背後に隠されているコンビニ強盗事件や鈴子の抱える不安などが現代社会の秘めている不気味さを巧みに浮き彫りにしている。
最後まで残った狩宮智里氏『歩く歩く歩く松の林のその雨の音を』は豊臣時代に活躍した絵師たちの物語であった。天下絵師の狩野永徳とその一門と、それに対抗するために七尾から京に出てきた長谷川等伯と娘のたづ。たづは絵師になるため男装して久蔵と名乗る。物語は回想形式で展開し、永徳と等伯との絵師としての葛藤と久蔵実はたづと永徳の子の光信との秘めた恋の物語が描かれていく。大胆なフィクションを交えながら絵師の業の凄まじさを綴った作品で物語も変化に富み、私は一番に推した。ただし背景に屏風絵を駆使する構成は安易で逆効果になるとの指摘もあった。
田辺剛氏『ある辺境にて』も魅力的な作品であった。架空の町の古い旅人宿が舞台で、突然国境線が変わり宿の真ん中が西と東の国の境になる。宿には無為に酒を飲んでいる亭主と内縁の妻、先妻の子の青年、その友人、娼婦たちが住んでいる。国境はその後もしばしば変わり、それを確認するため両国の兵士たちがやってくる。それらの人間の関係を通して土地に根差し現実にしか関心を持たない庶民のしたたかさ、都合次第でどうにでもなる権力の無責任さが描かれていく。それぞれの人間像が良く描かれていて、感傷を排した乾いたタッチの会話が優れていた。力量のある人だと思う。
藤澤大介氏『我が名は』は元禄赤穂事件を題材にした劇である。吉良邸の門前にある豆腐屋の政五郎は奇妙な成り行きで吉良上野介と知り合いになる。政五郎の見た上野介は世間の風評と違い「鬼にも仏にもなれないただの人」であった。上野介を天下の嫌われ者に仕立てたのは大石内蔵助の策謀で、それが討入りを正当化し彼らを英雄にしていく。情報社会で噂によって人間像が作られていく現代社会の姿を上野介の運命に託して描いた作品で面白く読んだ。
中国残留孤児の半世紀を越す人生模様を描いた杉本美鈴氏『大陸の花嫁』、詩的なイメージに溢れた今田三保子氏『睡蓮』、江戸の年中行事を織り込みながらからくりに人生を賭けた男を描いた円城寺三郎氏『江戸雪月花 からくりからべえ』も印象に残った。

第4回「近松賞」選評
選考委員 宮田 慶子氏
- 1957年生まれ
- 演出家
- 劇団青年座所属
- 第2回近松賞受賞作品「元禄光琳模様」演出
劇作の居どころ
最終候補に残った十作品は、題材も作風もかなりバラエティに富み、どの作品も大変興味深く読んだ。
「劇作」、ひいては「演劇」全体が、あまりにも広く多様になりすぎて、何を拠りどころにし、何を拾い上げていったらいいのか、まるで巨大な迷路の一角でジタバタしているような思いから、私自身、抜け出せずに長いこと居る。
“他力頼み”の謗りを承知しつつも、その突破口こそ、劇作家の持つオリジナルな視点と切り口、そして、演劇現場のすべての土台となる「戯曲の力」に、演出家の一人としては、大いに期待し、信じ、そして切望してしまう。
決して単なる啓蒙啓発の意味でなく、演劇として、今、発信できるもの、発信すべきものは、一体どんなものなのか――。その深い悩みと共に、候補作品を読み進めた。
各候補作の奥付けには、膨大な資料の索引が記されたものもあれば、インスピレーションの引き金を引いたもののメモもある。その表に目を通しながら、作者の頭の中を探ってみるのも、実はとても楽しい。
「作者はなぜこの題材にこだわったのか」を考えながら戯曲を読んでいくうちに、戯曲の内容の向こうに透けて見えてくる、作者の「居どころ」のとり方に、想像はふくらむ。
流されまいと必死に踏んばっているものには勇気づけられる。
しかし、かと云って、固執しすぎて、周りが見えなくなっているものには、かえって脆弱さを感じてしまう。作品(戯曲)の中に閉じ込もるのではなく、作者の目が、この世の中を何らかの形でとらえていると思われるものに、やはり共感と興味は湧く。
今回の受賞作は『螢の光』は、とにかくその独自の世界に強く引き込まれた。日常生活の情景を描きながら、綿密に仕組まれた時間設定や小道具などの要素が、情感を持ちつつも、数式や記号のような整合性を生み出している。
この両者を成立させることに成功したのは、まさに作者の「居どころ」と「世の中への視点」、そして資質としてのセンスや勘の良さに裏付けされているのだと思える。
「尼崎の北の突き当たりの市営団地」という地域性にこだわりながら、それ以外の土地がボンヤリとかすみ、まるでそこが、世界の中心であり、孤立しているのかのように錯覚させてくれる。
そこにだけ、やるせない濃密な空気が満たされているのだが、それはそのまま、身動きのとれない閉塞感に包まれた、この世界そのものに思える。
ミシンの内職で縫っているのが「犬の服」であったり、晴子と林をつないだものが、怪し気な「ペットボトルのおいしい水」であるという設定が、この閉じられた団地と世の中を相対化している意味で秀逸である。
個人的には、田辺剛氏の『ある辺境にて』の、硬質で安定した人物造形と台詞に好感を持ったが、「移動する国境線」という題材は、現実にそれを経験している国の作家による幾つかの秀作戯曲の切実さに、今一歩近付きたい思いが残った。





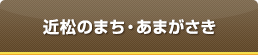

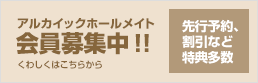







事実から遠ざかろうとする欲求
角ひろみ氏『螢の光』は、団地という画一化された家の中に住む人間の、解放への願望のドラマだ。
ただそれが屈折せざるをえないところに、この作品の面白味、特質があり、それはつまり団地というもののもつ面白味であり、特質であると作者はみたのだろう。
ソーメンのレシピで終わるという終わり方が象徴するように、およそ劇的とは思えぬ事柄が、生活の無気力を何かにつなぎとめる切実な問題となる。
苛立たしさを苛立たしく感じることなく、いわば受け入れて(妻の失踪さえも)見事に世間からはぐれてゆく。
失踪した妻は、内職のためのミシンの灯の点滅で合図をし合った団地の向かいの棟の林家の夫と失踪したらしい。が、果して二人の間に、それなりの結びつきがあったのか。
そこにある切実は、結びつくことの切実ではなく、むしろ、そこからいなくなることの切実であるのだと思える、そのことは何を意味するのか。
私には“事実から遠ざかろうとする欲求”だと思えてならぬ。
コンビニ強盗が30万円奪って逃げた、その日に妻は失踪した。
一週間後、妻の知り合いの女が、妻に借りたという30万円を返しにくる。
その30万円が重なる。が、その符号をほのめかすだけで、ふたつの事実に確かなつながりがあるのか。
作者はそこに踏み込もうとしない。そのことは、妻の失踪の事実を調べあげようとしないことに等しい。いずれもが“事実から遠ざかろうとする欲求”からくるものだ。
それは劇作家が“事実を超えようとする欲求”をもつがゆえのことだとも言えるが、そこにはまた、“事実に見返される”という宿命もある。
そこらあたりがこの作品の問題点だと私には思える。が、今は、この若い作家に“事実を超えようとする欲求”の方を見て、一票を投じた。だから言うのだが、その30万円など同じ30万円だと決めつけてしまえ。
そんなこと何をこわがる必要がある?林家の妻に対して失踪した妻の夫が「わかりません」と手をあげることは、広く大衆性をかく得してきた演劇に白旗をあげることに等しいような気がして私は嫌だった。
この作者には“事実から遠ざかろうとする欲求”に何が潜んでいるのかを知らしめてゆく責任があると私は思うしだいだ。
狩宮智里氏『歩く歩く歩く松の林のその雨の音を』は随所に劇的構造の面白さを感じた。第一幕の終わりに、新之丞が泣き、大人になった彼が赤児をあやして去るところ、光信が微笑んで左近に近づくかに見えて、久蔵に向かっているところ、など・・・。
陰と陽のあやなす面白さと言おうか。不満は、光信が絵師として久蔵に嫉妬している点が、事実のみに終わっていて、そこにあるドラマが書かれていないこと。
それがないから、二人の結びつきが、いわゆる仕事の出来る女を家庭に入れただけの話に終わってしまっている。
他にも田辺剛氏『ある辺境にて』、今田三保子氏『睡蓮』など、興味深い作品があり、初めて選考会にのぞんだにもかかわらず、粒ぞろいだったのではないかとの感想をもった。