選考委員
第3回「近松賞」選評委員のコメント

第3回「近松賞」選評
選考委員 太田 省吾氏
- 1939年生まれ
- 劇作家、演出家
- 京都造形芸術大学芸術学部教授

第3回「近松賞」選評
選考委員 栗山 民也氏
- 1953年生まれ
- 演出家
面白いものに、出会いたい。
隔年で行われる、この「近松賞」の選考会の時期が近づくたびに、妙に心が躍る。尼崎から送られてきた十本の最終候補作を前に、自分の演出作品だと思いながらまるで祈るような気持ちで、読み始める。
当たり前のことだが、演劇史を揺るがすようなとんでもない傑作に出会いたいと思う願望がまず先にたつからなのだが、その十本の作品から、その時代の光景がボンヤリと透けて見えてくるのも確かだ。
ニ年前の候補作の幾つかでは携帯電話が頻繁に使われ、そのたびに登場人物が「ちょっと、ゴメン」とうまいこと姿を消し、都合のいい時になると「ゴメン、ゴメン」と何食わぬ顔で勝手に戻ってくる。
そんないい加減な人物の出し入れがあるものかと、その時は大いに閉口したものだが、しかしよく考えてみれば、今の時代、携帯電話という男でも女でもない新たな登場人物が確かな生存権をもってしまっていることは、事実なのである。
では、今年はどうだったか。今の時代が、どのように映し出されていたのか。
一作、二作と読み進めていくうちに、どんどんと悲劇的になってしまったのは、わたしだけではないはず。残念だが全体に低調だったことは確かなことで、その主な理由は一つ、面白くないのだ。
戯曲の文学的価値を、構成、キャラクター、台詞などの視点から細かに云々するつもりではじめから読むわけではないが、そもそも戯曲とは生身の俳優による舞台上演のための台本なのだ。
構築が多少甘かったり、それぞれの場の配分が遊びになると決まって長く冗漫だったりと、たとえいくつかのキズがあったとしても、作者自身にも上手く制御できないほど勝手に暴れた格好で、こちら側に強く熱く手を差し出してくるような何かがあればいい。
全体の文学的な完成度を問う前に、いかに我々観客に、作者のほとばしる想像力の一つ一つがそれぞれの言葉によって、面白く開かれているかが大事であろう。
それが、一向に触れてこない。聞こえてこない。届いてこない。舞台上でぶつかり合い、刻々と変化する「動くドラマ」としての感触がない。
言葉が人間の声によって発せられるということへのまなざしが希薄なのだろう。つまり、人物がもう一人の人物と線を結ぼうと、もがいていないように思えた。
最近、読んだ本のなかに「コンフリクト・フリー」という言葉があった。
何の心理的葛藤ももたず、ただ支配をそのまま受け入れてしまうといった意味らしいのだが、今のわたしたちの人間関係の現在が、その言葉から炙り出されているようだ。
ならば、そんな時代の曖昧さが、人間に与えられた言葉の存在を虚ろにしているのか。
全体の印象を述べるだけで、選評とは程遠いものになってしまったが、今回はしょうがない。
十本のなかでは保木本佳子さんの『女かくし』を、わたしは推した。
狭い六畳の部屋で、まだ育っていない女が、一人の女へと必死に背伸びしようと夢想する姿が、関西弁の乾いた響きを伴って、嘘とまことの間を行き交う不確かな現代の生き物のように映った。
少なくとも、一番面白かった。

第3回「近松賞」選評
選考委員 別役 実氏
- 1937年生まれ
- 劇作家
独自のセンスとエネルギーを
全体に大人し目の作品が多かったように思われる。作品は、初動を与えられ、或る構想に従って動きはじめると、得てして予定調和的な方向に向かいはじめるのであるが、その種のものが多かったというわけである。
これを打破するためには、演劇的な独自のセンスとエネルギーを必要とするのであるが、今回の作品の多くには、この点が不足していた。
ただし、『女かくし』と『竹よ』には、かろうじてこれがあったと言えよう。
『女かくし』は、六畳の部屋を舞台とし、そこで暮す作家志望の女と男との、奇妙な関係を描いたものであり、そこに新しい感性を感じとらせるものの、それが演劇的にうねってこない。
つまり、独自のセンスは感じとらせるのだが、それを演劇的にどう形にするかというエネルギーが足りないのである。
途中、人魚の群れが登場するが、こうした場面転換でつなげようとせず、女と男だけ、どこまでこの関係をふくらませられるかを試みるべきであろう。
『竹よ』も、朔太郎の竹の詩をイメージの底に据えながら、現代の若ものたちのありようを探った、生々しい作品である。
三人の関係もよく出来ているし、科白も軽やかに交されていて、演劇的センスは感じさせるが、これも、構想の点で弱い。銃が出現するところまでは、この舞台全体の深層構造をうかがわせるのであるが、それがそのように使い切れていない。
後半、場面が変るが、これは恐らく、無意識に感じとったこの舞台の深層構造を、自分自身でわかりやすく図式してみたくなったせいであろう。
銃が発射され、意味もなく惨劇をもたらしてしまう、という場面で、突如としてこの舞台は幕を降してしまうべきであるが、その後のいきさつを言い訳けがましく付け加えなくてはならなくなったのは、この場面の切り換えでエネルギーを切らしてしまったせいである。
その他の作品では、尾崎放哉を題材にした『呵々大笑』(放哉挽歌)と、これも太宰治を題材にした『人間失格後~ グッドナイト 太宰治 ~』にそれぞれ興味を引かれた。
『呵々大笑』は放哉の死後、その葬儀のいきさつを物語る素朴な作風の戯曲であるが、その素朴さが意外にシアトリカルで、放哉について語るべき部分と、語る必要のない部分がややチグハグであるものの、好感の持てる作品になっていた。
『人間失格後』は、文字通り「人間失格」後を掘り起そうとしたもので、太宰治に対する思い入れの深さについては、見るべきものがあったように思われるが、太宰治が場面を換えて何人も出てきたり、人物設定に難があるように思えた。
他には、『風が舞い 風が立つ-ある家族の昭和戦後の歩み-』に注目したが、前半の満州引揚げから筑豊までは時代と登場人物たちの行動が、ダイナミックに連動して見えたが、大阪へ出てからの後半は、ややホームドラマのようになってしまっている点が、気になった。

第3回「近松賞」選評
選考委員 水落 潔氏
- 1936年生まれ
- 演劇評論家
- 毎日新聞客員編集委員、日本演劇協会常任理事
若い才能に期待した
最終選考に残った十作品はいずれも力作だったが、これと言って推せる作品は見当たらなかった。残念である。
保木本佳子さんの『女かくし』は、同棲している作家志望の女性とフリーターの男性の物語である。男は結婚しようと言い出すが女の方は不安を感じている。
男女の考え方のギャップ、今の若い女性の心理がスケッチ風に綴られていて、現代の一面を描いたまとまった作品になっていた。
ただし女の語る言葉が週刊誌の特集風の価値観、で私はそこにひっかかるものがあった。それは意識的でそのことで批評性を持たせていると言う意見もあって優秀作に選ばれた。
泉寛介さんの『竹よ』は萩原朔太郎の竹の詩をモチーフにした作品である。とは言っても、作品自体は無気力で怠惰な三人の若者の会話を軸に展開していく。
彼らは「文学が世界を変える」と語りながら、語るべき言葉を持っていない。朔太郎が生きた時代の輝かしい文学や言葉への信頼は今や求めることは出来ないという現代への批評である。
作品の構造もユニークで、突如として異質の二つの挿話が入ってくる。私は構造の斬新さは認めるものの、無意味な会話が続く(それが作者の意図である)ところが退屈で、作品としてはそれほど評価出来なかったが、優秀作に選ばれることに異議はない。
二作品とも作者は若く、若い才能に期待したいという全員の意見で優秀作が決定した。
外崎花牛さんの『呵々大笑』(放哉挽歌)は放浪先の小豆島で亡くなった自由律の俳人尾崎放哉を描いた作品であった。
劇は放哉が死んで葬儀に集まった人たちの言葉を通して、その人生を描き出すと言う構成になっている。
放哉の俳句は放哉の人間像と不可分で、放浪の人生が俳句仲間の井泉水、月花子、姉、別居中の妻、最後を見取った隣家の漁師夫妻などの話で描かれていく。
その手法が面白く漁師夫妻や島の子供たち、放哉が可愛がった知的障害の男などは実に良く描けている。
一方、当時の俳壇と放哉の俳句を説明するため月花子に長弁舌をふるわせるところや、姉や別居中の妻の人間像が不鮮明であるところに不満が残った。
野田治彦さんの『人間失格後』も「~ グッドナイト 太宰治 ~」の副題がついた太宰治の評伝劇であった。
彼が前半生を素材にした「人間失格」を発表した後、続編の「人間失格後」を執筆し始めたという設定で、太宰の人生が綴られていく。
作者はすでに何本もの作品を書き、いくつもの劇団で上演されている。この作品も構成や展開に練達の技が見え、技巧的には十作品中もっとも優れていたと思う。
ただし従来の太宰のイメージを超える内容があったかとなると疑問で、堀木とヒラメが彼を裏切る場面の設定と会話が無造作すぎる点も弱点になっていた。
中谷稔さんの『風が舞い 風が立つ-ある家族の昭和戦後の歩み-』は、満蒙開拓団の一家の敗戦から現代に至る三代に亘る歩みを綴ったドキュメンタリードラマであった。
波乱に満ちた歩みを感傷を抑えて淡々と描いた構成、展開に光るものがあった。後半になってややきれいごとになったが清々しい後味を残す作品であった。以上が印象に残った作品である。

第3回「近松賞」選評
選考委員 宮田 慶子氏
- 1957年生まれ
- 演出家
- 劇団青年座所属
- あまがさき近松創造劇場「風花」演出
「とらえ難い時代」への挑戦
今回は残念ながら大賞作品が出なかった。
最終選考に残った十作品は、題材もスタイルもそれぞれにかなりおもむきが異なり、その点では演劇の(戯曲の)多様性、表現の自由さが反映されていて面白いのだが、その持ち味を確立する要素が、いまひとつ足りなかった。
「戯曲」を書こうとするとき、描こうとする世界と、発信する相手である世の中との接点が、本当にとらえ難い時代なのだということを痛感させられた。
その意味において、優秀賞に選ばれたニ作品は、結果的に、「今の時代に戯曲を発信すること」といった、自分自身の立脚点を意識に置いた構造を持った作品になったと思う。
しかし、それは又同時に、「今の時代のとらえどころのなさ」を表現すること以上の「何か」を提示できないという、苦しい限界をも抱えてしまっているように思える。
作者独自の世界に深く潜行していくという手法は、ニ作品とも大変魅力がある。
しかし、多重性を持った他の要素のシーンの構成や関連性の置き方に、未消化な部分が残ったように思う。
メインで描くものに対して、それらが効果的に作用するためには、「視点の角度のずらし」なのか、「次元の移動」なのか、それとも「更なる深部へ向かう」のか、発想方法はさまざまなのだと思うが、戯曲全体の時間軸のおさまりが、納得できる形になってほしかった。
泉寛介氏の『竹よ』は、必然性の無効を狙った、果てしなく連鎖していく無意味な会話の部分は、企みが生きているのだが、途中で展開するプロレスと上(神)さんの場面は、サコタとタロウの会話で妄想的なオチがつく分、かえって宙に浮いたように思う。
保木本佳子氏の『女かくし』は、魅力的な台詞も多く、男と女の造形も楽しめるのだが、「人群れ」の存在がもっと明確に位置付けられると(例えばもっと毒を持つとか・・・)、主人公の女との絡みがふくらむように思う。
又、「繰り返す昼と夜」のイメージが、具体的に場面構成の中に取り込めると面白いと思った。
日常の生活の中で交わされる語彙数がどんどん少なくなり、人の口から発せられる言葉への思いが希薄になっている今、「戯曲」という形で何かを表現することが、本当に難しい時代になっているのだと思う。
「ダイアローグの不毛」を問題にする以前に、もはや「モノローグ」でさえ成立しないほど、言葉への信頼度がなくなり、言葉を扱うことに臆病にならざるを得ないのかと、暗たんたる思いにもなる。
けれど、その状況を映し出す意識も確かに必要ではあるのだが、「曖昧」なものを提示するための緻密な企みによる構成や、言葉の力を再認識させられるような簡潔で豊かな台詞達に出会いたいというのが、個人的に切望するところである。





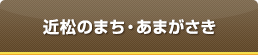

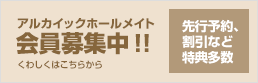







戯曲形式の意識を望む
最終選考に残った十作品、今回は題材のはっきりしているものが多かった、という印象を受けました。
江戸期を扱ったもの、戦後期の時代を扱ったもの、そして作家を扱ったものといった具合。
もちろん、それはそれで作者の興味の中心を表わしているということなのですが、往々にして、と私は思うのですが、それらの傾向として戯曲という形式が本当に必要とされているのかという疑問を感じさせられることが多かった。
舞台で演じられることを前提とする戯曲という形式は、物語を展開させるためには不自由な、制約の多いものです。しかし、その不自由さ、制約の多さは、スプリングボードでもあるわけです。
題材のはっきりしているものが多かったという印象は、物語の展開にとらわれ戯曲という形式がスプリングボードとなっていないと思える作品が多かったと言いかえてよいかもしれません。
優秀作品の二作は、舞台で演じることにそれぞれ工夫がなされていました。
泉寛介氏の『竹よ』は、現在戯曲を書いている自分を見つめようとしている作品で、その意識をただことばで語るのではなく、場面の構造で示そうとする工夫が興味あるものでした。
(プロレスラーの挿話と老人たちの挿話がその一つです。うまくいっていない、もっとよい挿話が考えられていいとも思われましたが。)
『竹よ』というタイトルは、萩原朔太郎への意識を表していますが、おそらく、朔太郎のことばに憧れを感じながらも、あのような<大きな>ことばを書けない現在のことばの情況を表わしているのでしょう。
「悲しき玩具」ともいえなくなっている現在の卑小なことばをひたすらしゃべる男たちは、朔太郎に照らされて意識化されている。こういった、戯曲を書くことの自己意識は、他の作品にないものでした。
保木本佳子氏の『女かくし』は、海の泡のように浮いては消えていく話題を連ねる作品で、これ以上モラトリアム状態をつづけられないといった年齢の男と女が、ややあせり気味に追われるように、通俗的話題をしゃべりつづける。
関西弁の明るい口調で。この女性週刊誌的話題をどう見るか、否定的な意見もあったが、現代の若者のしゃべりのリアリティーとして自覚されたものと評価された。
演劇的な工夫として、大勢の人々の群れが何度か登場する場面があるが、この人々の存在は、隣近所の世間の眼として描かれている、これではもったいない。
二人の生活をもっと遠くから見る者たちの眼としたら、二人の生が深みから射られることになったのではないだろうか。