選考委員
第2回「近松賞」選評委員のコメント

第2回「近松賞」選評
選考委員 太田 省吾氏
- 1939年生まれ
- 劇作家、演出家
- 京都造形芸術大学芸術学部教授
前・日本劇作家協会副会長

第2回「近松賞」選評
選考委員 栗山 民也氏
- 1953年生まれ
- 演出家
失われていく言葉を求めて
ある新作の台本が遅れ、非常に不安で過激な稽古場での日々を送っていたちょうどその頃、最終選考に残った十二本の戯曲が送られてきた。
そんな個人的な事情も絡んではいたが、まことにテンパッタ状況のなか、十二本の力強いドラマに出会えた。
全体的な印象から言うと、その多くの主人公、或いは物語の重要な担い手が、ほとんど老人であったこと。
作者の年齢が、いつもより少し高めということもあろうが、これは少し変だ。
他の登場人物で絡む若者たちの言葉は、平易に記号化された簡略な会話で書かれている、というよりはまるで音楽かリズム体のようだ。
今の若者から論理的に立ち上がる言葉が失われてしまって、ダイアローグが先に続かないというのか。
とにかく、老人を舞台の中心に据え、動きのテンポを少し落としながらも、失われていくドラマの会話を必死に積み上げようとした作品が多かったように感じられた。
選考は第一回目とは違って、早い時間で終わった。
その結果、保戸田時子さんの『元禄光琳模様』が第二回近松賞に選ばれた。
一回目が該当作なしであったから、事実上の第一回目の受賞者となるのだろう。
心から、おめでとうございます。
この元禄という時代に生きた絵師である尾形光琳の半生を描いた本作は、昭和から平成へとバブルの弾けていく前後の世相を元禄の時代に潜ませ、実にのびやかな展開のなか、乾いた叙事的な手法で一つの続き模様に仕立てた。
読み進めていくうちに、想像上の舞台はどんどんと時代の装飾をはずし、むしろ何もないガランとした空間に、言葉と身体によって色彩ある光景が次々と映し出されてくる。
それだけの自由な言葉の拡がりがあった。作者は登場人物たちに、いろいろな演劇的な仕事を課している。ただしラストのモノローグだけは、人間のせりふで終って欲しかったが。
また、今門洋子さんの、『南蛮煙管』を、私は嬉しく読んだ。
郊外の山里に建つログハウスを舞台に、倒産した会社の元社長が送る69歳のルネッサンスが、まるでジャック・タチ風のスケッチで、実に風通しよく描かれている。
幾つか細かな綻びはあるものの、今の時代に、小さな、しかし確かな光がキラキラ輝いて見えた。
受賞が決まり、だれ彼となく選考委員のなかから暖かな拍手が沸きあがったその時、尼崎市から、来年からの近松賞は当面休止との報告があった。
みごとな劇的ドンデン返しである。2000年に創設されてまだ二回、やっと歩き始めたばかり、それも今回272作品という記録的な応募作が集まり、それだけでも貴重な財産を得たはずなのだが。
市の財政事情がその理由と聞くが、公共性としての舞台芸術の有り様が、もともと採算が合わないから支援が必要だというのではなく、私たちの社会にとって演劇という芸術が絶対に必要な大きな力を持つものだという積極的な強い意志を、私たち一人一人がもつべきだろう。
これからの新しい人たちの新しい息づかいの聞こえてくる作品が、ずっと未来に向かってたくさん生まれてくることを願い、祈る。

第2回「近松賞」選評
選考委員 別役 実氏
- 1937年生まれ
- 劇作家
屏風絵のような展開
私は今回、保戸田時子さんの『元禄光琳模様』を受賞作として推した。この作品はタイトルに「模様」とあるように、華やかに花開いて散った元禄の文化と、それを支えた光琳と乾山の活躍を、さながら屏風絵のように展開したものと言っていいであろう。
ことさら目新しいドラマツルギーによったものではなく、登場する人物の把え方も特に目をそばだたせるほどのものにはなっていないが、にもかかわらず作品全体の「構え」がゆったりとし、或る広がりを見せている点に何よりも好感を持った。
昨今の現代劇が、ともすればメリハリを効かせすぎ、勢い「小造り」なものになってしまっていることから考えても、これは得難い資質と言えよう。
そしてまた、この作風はそのまま光琳の、装飾的でありながら職人芸になっていない作品の特色とも、つながっているのである。
作中、中ほどで「かきつばたの図」、最後に「紅白梅図」という屏風絵の傑作が示されることになっているのだが、この紹介の仕方がなかなか的確であり、全体像をくっきりと浮かび上らせるためのものになっている。
ただ惜しむらくは、江戸の武士文化と京の町衆文化との葛藤が、単に政治や経済のからみだけではなく、文化のうねりのようなものとして感じとりたかったのだが、その点については今ひとつ物足りなかった。
この点はまた、光琳と乾山との関係についても言えるのであるが、その美意識の違いと、そのそれぞれのその後の消長についても、たとえ暗示程度のものだったとしても、示しておいてしかるべきであったろうと思われる。
「元禄文化」というものは、一種のバブルのようなものであり、我々はどうしてもそれを、過日我々が体験したばかりの「バブル時代」になぞらえて見たくなるのであり、だからこそこの作品の今日的な雄弁さも見えてくるのであるが、それだけに、この時代の底流を成していた「文化」や「美意識」の変化を、いわば〈うねり〉として感じとりたいと考えるのである。
もちろん、妙な芸術論になってしまうのはつまらない。それらしいくだりがいくつかあるものの、それらはいずれも、意を伝えんとしてむしろ生硬さを目立たせ、演劇的ふくらみを失っているのである。
この点を考慮して、敢て深みにはまるまいとしているところもあり、それはそれで正解ではあるものの、「にもかかわらず」と、或る物足りなさを感じるのも事実なのである。
ただしかし、時代の登場人物を安定した距離間のもとに把え、それを動かした時代の流れを、これまた安定した視点で追い、そうした作業を通じて「時代の無意識」を探り出そうとする手法は出来上っている。
これに対する感受性を、更にふくよかなものにすることによって、内面への探りも深くなってゆくことと思われる。

第2回「近松賞」選評
選考委員 水落 潔氏
- 1936年生まれ
- 演劇評論家
- 毎日新聞客員編集委員、日本演劇協会常任理事
光琳の奔放な人生を描く
最終選考に残った十二編はいずれも力作であったが、保戸田時子さんの「元禄光琳模様」が受賞作に選ばれた。
元禄というバブル経済で文化が花開いた時代の中で、成金や権力を軽侮しながら、逆に権力を利用して自分の美の世界を作り上げた尾形光琳の人生を、弟乾山の視点から描いた作品である。
物語の展開にも工夫があり、候補作の中で最も纏まりのある作品であった。
注文を出せば何者にも縛られず奔放に生きたかに見える光琳自身の内的葛藤、時代への懐疑、死に対する怖れ、それを克服して美の境地を開く過程を描いて欲しい気がしたが、受賞作に相応しい優れた作品である。
辻本久美子さんの「蒼い風が聴こえる」も印象に残る作品であった。六人の若者の昭和十一年から現代に至る数寄な人生を綴った作品で、六人それぞれの人物像を書き分けた力量は大したものである。
物語にも変化と起伏があって展開も面白いのだが、逆にそのために話を作り過ぎているところが目についた。登場人物が余りに都合よく出会う箇所がいくつかあり、そこが減点になった。しかし、劇作家として十分活躍していける人だと思う。
坂本正彦さんの「犬吠という名の岬」は、現実にあった保険金殺人事件にヒントを得た作品であった。
スナックの経営者の金村が、社会から落ちこぼれた人間たちを集め、酒とあやしげな薬を飲ませて死に追いやっていく姿を綴った物語で、現代の人間模様が出た作品であった。
一見親切そうで底に凄みを湛えた金村の人間像が良く書けていた。しかし、現実の事件の方がはるかに恐ろしい相貌を持っている。現代の不気味さである。
辻野正樹さんの「天国(うえ)を向いて歩こう」も、世間を騒がせたネット心中を扱った作品であった。司馬という男の呼び掛けで、五人の男女が心中するために空室になっているアパートの一室に集まってくる。
それぞれ死にたい理由は違い、死に方を巡っても意見が対立する。
前半はブラックユーモア風な展開で会話も面白く書けていたが、押入れから現金輸送車を襲った犯人が隠していた二億円の金が見つかり、それが混乱を呼んでいくところから構成が乱れていった。
今門洋子さんの「南蛮煙管」はバブルがはじけて山林投資で借金を作った造園業者の老人一家の物語であった。
彼と彼の片腕になって働いてきた老職人が、すべてを無くしたのに再生を夢見て、家族が連帯感を取り戻すまでがホームドラマとして展開する。
纏まりのある作品でほのぼのとした味があったが、受賞作にするには物足りない気がした。
そのほか雪丸未来さんの「いまそこで終わった世界」の詩的イメージに溢れた世界、嶽本あゆ美さんの「冥途の飛脚」の修羅の世界を描いた作劇にも心魅かれるものがあったが、どちらも作者の思いだけが先行した作品であった。
全体を通して水準が高く、現代社会の様々な姿に取材した意欲的な作品が多かったことも特色であった。
二回目にして受賞作を選べたことを素直に喜びたい。二十年以上に亘ってこつこつと劇作を続けたという保戸田さんに改めて「おめでとう」の言葉を送る。

第2回「近松賞」選評
選考委員 宮田 慶子氏
- 1957年生まれ
- 演出家
- 劇団青年座所属
- あまがさき近松創造劇場「風花」演出
熟成の作品
確かな構成力と、目配りの行き届いた人物配置・・・・。
永年あたためていた作品に、更に幾度も手を加えて今回の応募に至ったという経緯をうかがい、成程と納得いたしました。
“熟成”という時間を重ねた貫禄すら持ちあわせた、138枚の力作だと思います。
元禄の世を生きた尾形光琳という巨人を題材にした「元禄光琳模様」は、オーソドックスとでもいえる正攻法の作劇方法によって書かれています。
けれど、それは決して“古い”という意味ではなく、作品の安定感と、この題材にふさわしいゆったりとした優美な世界を生み出すのに有効な方法であったと思えます。
十人の主な登場人物達は、それぞれが独自の役割を担い、光琳を中心核として四方八方に枝をのばし、鮮明な人間パノラマを形(かたち)作っており、そのために、いわば「たった十人」で、光琳を取り巻く元禄という時代の多面性を描くことに成功しているといえます。
プロローグとエピローグに登場する、光琳の弟・乾山の扱いに関しては、客観的な視点を持つ狂言廻しの役割として、もっと頻繁に中身のエピソードに介入しても・・・・という考え方もできますが、二十年間ほどにも及ぶ壮大なドラマの末、エピローグでの登場に、何故かホッとさせられる効果が生きているように思います。
あえて私なりに気になっている点を申し上げるとするならば、破天荒で女好きで、俄か成金達に反抗する光琳の、絵師としての本当の心の拠りどころ、そしてドラマとしての、主人公光琳の葛藤や破綻の描き方に、もうひとつ踏み込みが欲しい気がします。
“京の町衆の自負”というものが、もう少し具体的に書き込まれると理解しやすくなるのかもしれません。
又、江戸に行った光琳が、嫌気がさして再び京に戻ろうとする動機も、いささか淡泊に思えます。
絵師として自由であろうとする精神と、反抗しようとするが故に俗世にからめとられていくという矛盾のハザマで、激しい本性の刃は、一度は己れ自身に向かうのではないか・・・・という想いが、天才画家に対する、我々凡人のロマンなのかもしれません。
しかしながら、スケール感のある骨太で端正な作品であり、演出家としては舞台構成や人物造形にアレコレと思いを巡らせたくなる、優れた作品だと思います。
最終選考に残った十二作品は、それぞれ作風の異る、レベル以上の作品揃いでした。辻本久美子氏「蒼い風が聴こえる」、嶽本あゆ美氏「冥途の飛脚」も、心に残った作品です。
常々私は、演劇の世界を、絵画の世界と引き較べ、共通点や相違点につらつらと思いを馳せます。
絵描きが、何年もかかって一枚の絵に筆を加え、一歩一歩“自分の絵”に仕上げてゆく過程を知ると「我々演劇の世界もかくありなん」と勇気づけられます。
その意味においても、今回受賞なさった保戸田氏の永年の作業に、あらためて敬意を表したいと思います。





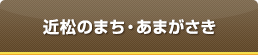

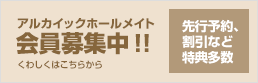







オーソドックスな描法で
本賞初の大賞受賞作、保戸田時子さんの『元禄光琳模様』は、タイトルで示されているように、尾形光琳を扱い、絵師としての生き方を元禄という時代の中で、大名や公家との葛藤をもつ町衆としての心意気を保持しようとする人物として描いた作品である。
現代感覚をもったオーソドックス描法によって時代と人物を描かれているというのが私のこの作品への評言だが、そこには説明が要る。
【現代感覚】による時代、人物の描法は、往々にしてパロディーとして発揮されるもののように思われるが、この作品での【現代感覚】 は異っていた。
そして、"オーソドックス" といっても、時代や人物をオーソドックスに描くというときに思い浮かぶ手法とは異なるものをもっていた。
パロディーとか、批評を【現代感覚】の発揮としようとするせせこましさを超えようと、対象を自分の正面へ据えようとしている姿勢があり、それが作品全体の、ゆったりと鷹揚なといった印象を形成している。それが"オーソドキシー" を感じさせるところであった。
そして、"オーソドックス" な手法で時代や人物を描くとすると、当然のように用いられる"時代らしさ語"、たとえば「○○でござる」式の用法パターンや地方語のなぞりがこの作品では避けられている。
そこに、時代性や地域性をパターンで表現しようとする手法を超えようとしている【現代感覚】を感じた。
さらに、それは現在標準語に翻訳するという単純化でもない言葉で書かれている。そしてそれが充分に時代や地域を感じさせている作者の力に感心させられた。
問題点としては、エピローグ。不要とはいいきれないが、再考、改訂の必要あると思われるところです。「紅白梅図屏風」で幕を降すというのは素敵な図ですが、まとめの図、いかにもの図ともなり、この戯曲では小さくおさめてしまったという感をまぬかれませんでした。上演の折には改訂を要するところでしょう。
作者には、大劇場演劇にしっかりとした作品を提供する作家としての力が認められます。
候補作の他の作品の中では、坂本正彦さんの『犬吠という名の岬』が注目されました。有名な保険金殺人事件を描いた作品ですが、現在の日本の基底で動いている"すさみ"が、この作品では登場人物たちの躁状態とだるさの共存状態として描かれ、そこにリアリティーを強く感じさせられる作品でした。
受賞作とは並べて比較するというわけにいかない(異分野といっていいほど異る)作品ですが、この作品だけを取り出して見てみますと、しかし舞台としての工夫に欠点があるように感じました。
演劇的には平板、常識的であり、この優れたリアリティーを演劇的にどう発揮するかにもう一工夫が要ると感じました。