選考委員
第1回「近松賞」選評委員のコメント

第1回「近松賞」選評
選考委員 太田 省吾氏
- 1939年生まれ
- 劇作家、演出家
- 京都造形芸術大学芸術学部教授
前・日本劇作家協会副会長

第1回「近松賞」選評
選考委員 栗山 民也氏
- 1953年生まれ
- 演出家
「場」と「人」の予感
11月1日、尼崎市内のホテルで選考会が行われたが、大賞「近松賞」の該当作は残念ながら見つからなかった。
副賞300万円は、芝居を創るものたちには充分スキャンダルである。
ただそのスキャンダル性のことではなく、新たな戯曲賞の出発に見合うだけの演劇の力が、我々選考委員を動かさなかった。
候補作11編を読んだ時、そして日本演劇の現在の有り様にまで話が及んだ選考会の席上での感想などから、僕なりの意見を一つ。
戯曲の書き手は、演劇という劇世界のあらゆる可能性に向かって、自分の描きたいモチーフをどのように言葉にしてゆくのか、その書き手の熱い魂のような衝動が登場人物に具体的な台詞を喋らせ、場面を構成してゆく。
戯曲は、舞台作品を上演する為の核であって、素材ではない。
たとえ、乱暴に自分なりの感覚だけで押し切ったものでも、自由奔放に今までの演劇スタイルを自在に壊したものでもそんなことは構わない。
台詞や状況が生まれた背景にどんな書き手の衝動があったのか、そして、その衝動がどんなプロセスを経て一つの作品へと立ち上がって来たのか。
これは、一演出家である私の全く個人的なドラマへの強い思いでもあるのだが、画家が何故に新しく白い画布に絵の具を重ねてゆくのかという作業に似ている。
つまり、その画家の目には何が映り、何を選びとったのか、そして、その見つめていた対象物をどのように自分が見ようとしたのか。勿論、演劇はその戯曲を核として、演出家が介在し、ある時は音楽が必要になるだろうし、その全体を具体化するのは動く肉体を持った俳優であるのだから、より多視点の積み重ねの上に成り立つものだ。
そんなこと百も承知と言われそうだが、果たして、そんな強い書き手の衝動から生まれたドラマに出会うことはなかった。
候補作のなかには、今の時代の照射からか、物語の不成立のなかで現代の印象を透明なかたちでスケッチしたものや、しなやかで平易な台詞をあっけらかんとした家族に託して繋いでいった作品など、自由に、いつのまにか引き込まれてしまった佳品もあったが、それは一つの可能性が見えていたのであって、一つの劇空間がそこから拡がる可能性にはなりえていなかったように思える。
最終選考の結果、菱田さんの「いつも煙が目にしみる」と宮森さんの「十六夜―いざよい―」が残った。話し合いの時間も、この2本に長く使われた。
私は菱田さんの作品を小品ながらも強く推した。阪神大震災後の仮設住宅に、1人で住む女と、その彼女にインタビューをする新聞記者との関係を軸に、戦後の闇の底辺に生きた女達のカストリ雑誌への取材が、随所に挟み込まれる。
構成上の問題や役柄の類型的な扱いに不満は残ったが、シンプルな技法のなかで、とにかく人間の肉声が聞こえてくるように思えた。崩壊の煙が今も漂っているかのような「場」に欲望に満ちた「人」が生きている現実の予感がしみるように伝わってきた。
戯曲賞は、それ1本の作品に対しての評価というより、これをバネに次回作へのジャンプを期待するものだと思う。第2回目の「近松賞」作品を楽しみに待つ。

第1回「近松賞」選評
選考委員 別役 実氏
- 1937年生まれ
- 劇作家
力感に乏しい
「近松賞」という大きな賞が出来、選考を委ねられた者としても、大いに期待した。
そして、最終選考に残った11本を見る限り、かなり水準の高いものが集まった、との印象を持った。
しかし、これはここへきての演劇界全体の問題でもあるが、全体にこづくりにまとめあげたもの、整ってはいるが力動感に欠けるもの、が多かったような気がする。
私が、一番高い点数をつけた宮森さつき氏の『十六夜―いざよい―』も、その典型だったと言っていいだろう。
この作品は、タイトル通り十六夜の月の夜に、それを賞でるべく或るアパートの一室に集ったひとりの男と3人の女と、もうひとり幻想の女との、いわば「人間模様」を描いたものであり、一読後私は、「まるでローランサンの絵のようだ」と思ったが、軽やかな対話でつながれたその情景は、淡い寂寥感をたたえて美しく、同時に安定している。しかし、如何にも力動感に乏しい。
もちろん、何か事件が起きて、場面がダイナミックに変転しなければならない、と言っているのではない。
たとえばこの「人間模様」にしても、叙述的ではなく造形的に組み立てられていれば(それには、水島の存在感が弱い)そこに観客は、ダイナミズムを感じとることも出来るのである。
ニューヨーク帰りの姉が、最初にジョークとして、弟にリンゴの土産を渡すところがある。
最後にまたこの姉は、「本当のお土産」として弟に或るものを渡すのだが、これもリンゴなのである。
言うまでもなくここには、「リンゴを予定していたものにとって、最も意表を突くものは?」という思考が働いているのだが、実際の観客は、それほど意表を突かれない。
細かいことを言うようだが、この種の思考もまた、ダイナミズムを失わせているのである。
もう一本の優秀作である菱田信也氏の『いつも煙が目にしみる』に、私はあまり高い点数をつけなかった。
確かに、一読して或る感動を覚えたのは事実であるが、阪神大震災後の現実と、終戦直後の現実を、対比させながら同時進行させる方法に、ややありきたりのものを感じとってしまったのである。
この作品は、阪神大震災後の仮設住宅に住むひとりの女性を社会部の記者である男性が取材のために訪問する、という場面を現在形でつなぎとめながら、かつてその記者の祖父がカストリ雑誌の一記者として、終戦直後の我国の混乱期を生きた女性たちを取材する場面を、重ねあわせてゆくものであるが、もしこの場合、「社会部の記者」というものと「カストリ雑誌の記者」というものの、社会に対するアプローチの差、的確に構造化されていたら、それからこれへの女性史のドキュメンタリーとして、秀れた作品になっていたであろうと思われる。ただこれは、ほとんど女性の「一人芝居」であり、それをここまでつなぎとめた筆力は、見るべきものがあると言っていいだろう。

第1回「近松賞」選評
選考委員 水落 潔氏
- 1936年生まれ
- 演劇評論家
- 毎日新聞客員編集委員、日本演劇協会常任理事
力作揃いだったが
最終選考に残った11作品は、いずれも力作で、近松賞応募作の水準の高さを思い知らされた。しかし、大賞にふさわしい作品はなく、優秀賞2篇を選ぶことで終わった。
全国から198人、208作品の応募があり、近松賞が劇作家を目指す人々の大きな目標になっていることを考えると、この判断は妥当であったと思う。
優秀作の内、私は宮森さつきさんの「十六夜―いざよい―」を評価した。
姉弟と弟の恋人、姉の同僚、そして姉の友人だった奈々の幽霊が、十六夜の月を見ながらアパートの一室で話を交わすという会話劇で、その会話の中から姉の道子はキャリアウーマンで、弟の孝一は自分の道を見つけかねていること、恋人の由佳は自殺未遂の過去を持つことなど、それぞれの人生が透けて見えてくる。会話が良く書けていて、現代社会の中で浮遊しながら生きる人間の姿が浮かびあがってくる。
叙情性があっていい作品だと思ったが、淡彩でこじんまりまとまり過ぎている。そこに不満を感じた。
菱田信也さんの「いつも煙が目にしみる」は、阪神大震災から1年後、仮設住宅に住む34歳の女性を訪ねた新聞記者のインタビューと、終戦直後、記者の祖父でカストリ雑誌の記者だった男と、当時の社会の中でたくましく生き延びた女性たちとのインタビューが、並行して展開していくという構成で、廃墟となった社会で生きる人間像を通して、人間の生の意味と現実をSEXを軸にして描いた作品であった。
同じ廃墟といっても時代と状況によって感覚が違うし、男性と女性では考え方に違いが出る。幸不幸という言葉をとっても、個々の人間にとっては意味も考え方も違う。
外部の人間と当事者にとっては価値観も異なる。
多彩な人物とのインタビューという形で、生きる意味を問う構成と展開に面白さがあったが、スケッチを重ねていく印象もあって、ドラマとしての求心力に弱さがあったように思う。
選には洩れたが、私自身は吉川進さんの「さくらふる」、いくたけんさんの「こじきおやじ 闇よりおのずからほとばしる光よ。」も面白く読んだ。
吉川さんの作品は、アル中気味の父親と一家を支える母親を中心に、2人の息子、2人の娘たちの姿を描いた作品で、ごく平凡な家庭を舞台に、家族の絆を求めながらうまく行かない親子や兄弟の関係を描いた作品であった。
全員が不器用で、現代にも家族にも要領よく対処出来ない父と子どもの姿と、理屈ではなく現実に対応していく母親がよく描けていたと思う。
いくたさんの作品は、ホームレスと呼ばれる人たちの社会を通して見た現代社会の乾きを描いた作品で、現代のメルヘンと呼べる作品であった。
島田九輔さんの「青楓の繁る家」は巧さを感じさせる作品だったが、すでに上演されている「唱歌元年」や「漱石山房の人々」に比べると、素材そのものが趣向の段階に止まっている気がした。

第1回「近松賞」選評
選考委員 宮田 慶子氏
- 1957年生まれ
- 演出家
- 劇団青年座所属
- あまがさき近松創造劇場「風花」演出
人間に踏み込む言葉として
まずは正直に言って「208作品」という応募数に驚いた。
常日頃、台本探しに血眼になっている演出家のひとりとしては、「一体何処にこれだけたくさんの才能と台本がかくされていたんだ!?」と、嬉しさと口惜しさが入り混じった思いだった。
そしていよいよ最終選考に残った11作品を読む作業にかかった。
確かにさすがにあるレベル以上の作品ばかりである。けれど、惜しいことに“手ごたえ”とでもいおうか、なかなかガツンという感覚がない。
どうもこちらを揺さぶってくれない。何故なんだろう…。
テーマや題材は個々それぞれだ。着眼点や構成の面白いものもある。
だが戯曲の言葉は最終的には、原稿用紙の平面から立ち上がり、舞台という立体三次元の空間に成立しなければならない。
それも役者という生身(なまみ)の肉体に乗せ得る“生きた言葉”でなければならないはずだ。
―できるならば、観念的な言葉遣いでなく、紋切型の会話にならず、その人物の深みや裏側を想像させてくれる台詞であってほしい。―
演出をする者としては、どうしても戯曲に対する期待や要望がふくらんでしまう。
芸術分野の中でも唯一“人間”を素材として扱う「演劇」だからこそ、一歩も二歩も“人間”の中に踏み込む作業をしたい。それは絶対に、戯曲の力であると思うのだ。
…という訳で、選考の結果残念ながら近松賞には届かなかったが、それぞれ個性的な2作品が優秀賞に選ばれた。
菱田氏の「いつも煙が目にしみる」は、“女”というものが描けていることに拍手を送った。
震災後と戦後を重ね合わせ、その中を生き抜く女達の原始的なヴァイタリティーを描くと同時に、ひそかに抱える底無しの虚無感を感じさせてくれる。
それはまた、性別を超えて、21世紀初頭である現代の世相をも浮かび上がらせてくれるのだが、もう一方の男達の、祖父から孫へつながる糸譜との接点がうまく絡んでこない。
宮森氏の「十六夜―いざよい―」は、ささやかな日常を描きながら、かわされる会話が通俗におちず、各人物の発する言葉としての面白さと説得力がある。
変化球を含んだ会話のキャッチボールにリズムがあり、また、各人物の心の中が、決して表層的でなく、矛盾と共に幾重にも堆積した複合物として見えてくる。
人の出入りの展開など、構成にもう一工夫ほしいが、人物像(特に姉の)の魅力は大きい。
次回の近松賞にとても期待している。ぜひとも、演出家や役者をガツンと一発殴ってくれるような台本を待っている。
すべての面白い芝居は、戯曲からはじまる。だから戯曲はスゴイのだ。現場がドンと乗りかかれる舟を、切に待ち望んでいる。





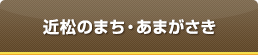

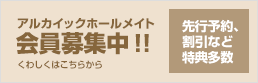







戯曲=演劇形式にバネを!
戯曲というものをどういうものとしてとらえるか。
言いかえれば、他の表現形式では描けないところがその作品でどう発揮されているかがやはり大事なところだということが選考の場ではいつもあらためて感じさせられる。
テレビや映画の方がふさわしくはあるまいかと思えたり、小説の方がと思えたりするのは不成功ということになる。
俳句を考えてみればわかりやすいと思うが、五七五は制約といえばきわめて強い制約だがあの五七五は他の形式では決して描けないものごとが展開することを可能とするバネでもある。
戯曲という表現形式には、小説やシナリオよりも詩や俳句に近いものがあるのかもしれない。制約の強さとそれがバネへ反転するところ、そこにより強い意識が必要とされるということである。
受賞作は、描いた世界、空気、人物に優れていたと同時に、その戯曲構造の意識の働きにすぐれていたともいえるものだったといっていいだろう。
菱田信也氏の『いつも煙が目にしみる』は、阪神大震災後の仮設住宅に1人住まいする女と、戦後の社会を生きる女たちを並存させて女たちの一筋縄ではかたづけられない生のリアリティーが重層していく。
実際の演出は易しくないが、同一空間の中で二つの時代が描かれ、だからこそ【重複】する。舞台という制約ある空間が、だからこそという力を発揮している。
宮森さつき氏の『十六夜―いざよい―』は、舞台空間を、大きな事件が起らなくとも成り立つものとして、月見に集った男と女の日常的な時間を描きながら、その淡彩さを崩さぬままに、幽霊という非日常的存在を出現させることで、舞台という空間の変幻性を活用しているところが評価されたように思う。
これら受賞作におとらず戯曲=演劇構造に意識的だと思われる作品があった。飯田茂美氏の『あなたのもとめるものすべて』である。
短い7つの場で展開されるオムニバス的な構成の作品で、舞台という空間を、人為によって設えられて成立しているにすぎない空間として意識された知的な作品だった。
ここで描かれたのは、明るい調子でしか語れないニヒリズムによって照明された世界であり、こういった世界観に強いものを感じた。
しかし、その基準を形成しているオムニバス的構成が、作者の世界展開に【都合のよい】ものとなり、人間の登場という演劇の基本的成立条件を薄くしているように感じられ、人形劇の台本としたら、といった感想をもたせられ、そこが欠点としてうつり、残念だった。
この賞には多くの作品が寄せられた。残念ながら大賞は出なかったが、主催者である尼崎市には、並々ならぬ熱意がある。
応募作品数の多さにも、【近松】の名にふさわしい優れた演劇作品を生み出そうとするその熱意が表れているのだろうが、選考会では、市長が始めから終りまで経過を見守りつづけておられた。
優れた作品を産む賞として、次回以降の応募作品に期待したい。